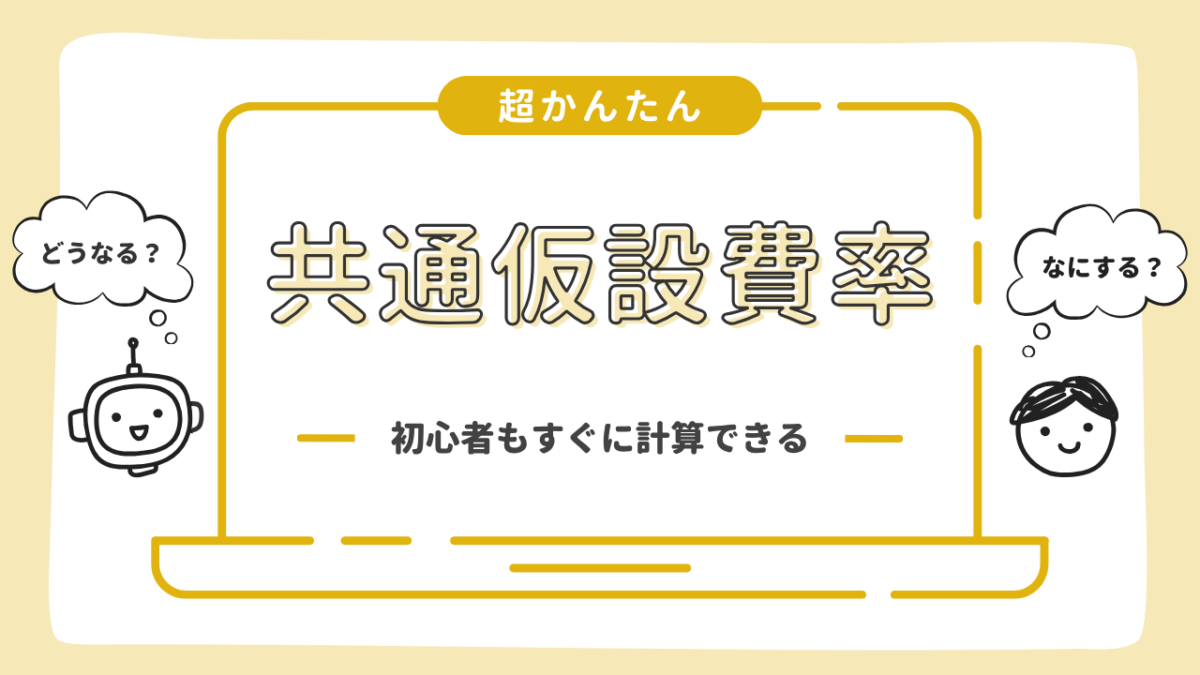「共通仮設費は高すぎると失注する…」
「一体何パーセントが正解?」
一般的に共通仮設費率は直接工事費の3~12%程度の範囲で変動しますが、この幅の広さこそが積算担当者を悩ませる要因となっています。
現場ごとのシミュレーションから、すぐに使えるExcelテンプレート、根拠となる計算式、プロが陥りがちなミスの罠まで、自信を持って共通仮設費を算出するための知識とツールを1つにまとめました。
CONTENTS
共通仮設費率の計算ツール
実際の工事現場で共通仮設費がどのように算出されるのか、具体的な数値を用いたシミュレーションを通じて理解を深めていきましょう。
たとえば、工種が「建設新営」、直接工事費が「20,000千円」、工期「12ヶ月」を例に取ると、共通仮設費率は国土交通省の積算基準に基づいて「8.22%」となります。
※ 国土交通省「公共建築工事共通費積算基準」(令和5年改定)
共通仮設費率が計算できるExcelテンプレート
共通仮設費率の計算がExcelやスプレッドシートで簡単にできるテンプレートを用意しました。無料でダウンロードできて、すぐに使えます。

共通仮設費率の標準的な計算式
国土交通省が定める共通仮設費率の計算式は、次のとおりです。一見複雑に見えますが、数値を当てはめるだけで算出できます。
共通仮設費率(Kr) = Exp(a + b × LogeP + c × LogeT)Pには直接工事費を千円単位、Tには工期を数ヶ月単位で入れます。a、b、cは工種で差があるため、以下の表の数値をあてはめます。そのため、工事の種類で共通仮設費率のパーセンテージは変動します。
| 工種 | a | b | c |
|---|---|---|---|
| 建築新営 | 3.346 | -0.282 | 0.625 |
| 建築改修 | 3.962 | -0.315 | 0.531 |
| 電気設備新営 | 3.086 | -0.283 | 0.673 |
| 電気設備改修 | 1.751 | -0.119 | 0.393 |
| 機械設備新営 | 2.173 | -0.178 | 0.481 |
| 機械設備改修 | 2.478 | -0.173 | 0.383 |
| 昇降機設備 | 4.577 | -0.323 | – |
※ 国土交通省「公共建築工事共通費積算基準」(令和5年改定)
共通仮設費率の上限値と下限値の計算式
共通仮設費率には標準的な計算式以外にも、許容される上限と下限の計算式があります。工期に左右されずに、工事の規模のみで設定できます。
共通仮設費率(Kr)の上限値 = a × P^c
共通仮設費率(Kr)の下限値 = b × P^cPには直接工事費を入れます。aは工種別の上限値係数、bは工種別の下限値係数、cは工種別のパーセンテージです。また、工種別に直接工事費の額によって、計算式がわかれます。
| 工種 | 1,000万円以下 | 1,000万円超 |
|---|---|---|
| 建築新営 | 3.25~4.33% | 4.34×P^0.0313~5.78×P^0.0313 |
| 工種 | 500万円以下 | 500万円超 |
|---|---|---|
| 建築改修 | 3.59~6.07% | 6.94×P^0.0774~11.74×P^0.0774 |
| 電気設備新営 | 3.90~7.19% | 9.08×P^0.0992~16.73×P^0.0992 |
| 機械設備新営 | 4.86~5.51% | 10.94×P^0.0952~12.40×P^0.0952 |
| 工種 | 300万円以下 | 300万円超 |
|---|---|---|
| 電気設備改修 | 1.91~5.21% | 3.10×P^0.0608~8.47×P^0.0608 |
| 機械設備改修 | 1.73~4.96% | 2.44×P^0.0433~7.02×P^0.0433 |
| 工種 | 1,000万円以下 | 1,000万~5億円 | 5億円超 |
|---|---|---|---|
| 昇降機設備 | 3.08% | 7.89×P^-0.1021 | 2.07% |
※ 国土交通省「公共建築工事共通費積算基準および公共建築工事標準単価積算基準の改定について」(2011年4月)
共通仮設費の計算方法
共通仮設費で最も基本となる計算式は、次のとおりです。
共通仮設費 = 直接工事費 × 共通仮設費率 × 各種補正係数| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 直接工事費 | 材料費、労務費、直接経費の合計額。さらに支給材料費、無償貸付機械の評価額、処分費なども控除する場合は「対象工事費」と呼ばれる。 |
| 共通仮設費率 | 直接工事費の規模に応じて、国土交通省や各自治体が定める標準率表から該当する率を選択する。 |
| 補正係数 | 工事の特殊性に応じて、地域係数、工期係数、施工条件係数などを乗じて最終的な率を算出する。 |
1. 直接工事費
直接工事費とは、建設工事の積算において、建物や構造物などを完成させるために「材料費、労務費、直接経費」を足した費用です。
| 項目 | 詳細 | 注意点 |
|---|---|---|
| 材料費 | ①コンクリート、セメント、砂、砂利 ②鉄筋、鉄骨 ③木材、合板 ④タイル、ガラス、塗料 ⑤電気配線材、配管材 | 資材の購入費、荷造り費、運搬費を含む。 |
| 労務費 | ①大工、左官、鳶、電気工、配管工などの職人の賃金 ②残業手当、休日手当などの割増賃金 | 現場監督や現場事務員など、直接作業を行わない管理者の給与は、通常「現場管理費」に含まれ、直接工事費には含まない。 |
| 直接経費 | ①建設機械(クレーン、バックホウなど)のリース料や損料、燃料費、運転労務費など ②特殊な工法や技術を使用する場合の特許使用料 ③工事施工のために使用した電気、水道、ガスなどの使用量 | 材料費と労務費以外で、個別の工事の施工に直接関係して発生する費用。 |
2. 共通仮設費率
共通仮設費率の標準的な計算式や共通仮設費率の上限値と下限値の計算式で計算します。共通仮設費率の計算ツールを使うと早いです。
また、共通仮設費率の大まかな早見表は、次の通りです。
| 工事規模 | 直接工事費 | 標準的な共通仮設費率 | 共通仮設費額 |
|---|---|---|---|
| 小規模工事 | 10,000千円 | 8.5~12.0% | 85~120万円 |
| 中規模工事 | 50,000千円 | 6.0~9.0% | 300~450万円 |
| 大規模工事 | 100,000千円 | 4.5~7.0% | 450~700万円 |
| 超大規模工事 | 500,000千円 | 3.0~5.0% | 1,500~2,500万円 |
工事規模が大きくなるほど共通仮設費率は低下する傾向にあります。これは規模の経済性が働くためで、仮設事務所や安全設備などの固定的な費用が工事規模に比例して増加しないことが理由です。
3. 各種補正係数
実際の積算では、このような基本率に加えて、工事場所による補正(市街地係数1.5倍など)、工期による補正(冬期施工1.2倍など)、施工条件による補正(夜間工事1.3倍など)を組み合わせて計算します。
たとえば、都心部での夜間工事で直接工事費1億円の場合、基本率5.78%に市街地係数1.5と夜間工事係数1.3をかけると、最終的な共通仮設費率は11.27%となり、金額にして1,127万円が計上されることになります。
共通仮設費の計算でミスする3つの罠
1. 現場の特殊条件を見落としてしまう
共通仮設費の計算で最も陥りやすいミスが、現場固有の特殊条件の見落としです。標準的な積算基準書には記載されていない、その現場特有の制約条件を見逃してしまうと、工事着手後に追加費用が発生し、利益を圧迫する要因となります。
典型的な見落としやすい特殊条件には、以下のようなものがあります。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 搬入路の制限 | 狭小な進入路により小型車両での運搬が必要 |
| 作業時間の制限 | 病院や学校周辺での騒音規制による夜間工事 |
| 地下埋設物の存在 | 既存配管や地下構造物による施工制約 |
| 近隣協定による制約 | 地域独自の環境保全協定や景観条例 |
失敗例として、ある工事では鉄道近接工事であることを考慮せず、列車見張り員の費用を計上し忘れたケースがあります。6ヶ月の工期で「見張り員2名×日額2万円×180日=720万円」もの追加費用が発生し、工事利益がほぼゼロになってしまいます。
2. 工事内容に応じた率補正を忘れる
標準的な共通仮設費率をそのまま適用してしまい、工事の特殊性に応じた補正を忘れるケースも非常に多く見られます。実際の工事現場では、標準的な条件で施工できることはむしろ稀であり、何らかの補正が必要となることがほとんどです。
主要な補正項目と補正係数の目安は以下のとおりです。
| 補正項目 | 補正係数の範囲 | 適用条件の例 |
|---|---|---|
| 市街地補正 | 1.3~1.5 | 交通量の多い市街地、住宅密集地での工事 |
| 山間部補正 | 1.2~1.4 | アクセス道路が狭い山間部での工事 |
| 冬期補正 | 1.1~1.3 | 積雪地域での冬期施工 |
| 夜間工事補正 | 1.2~1.5 | 交通規制により夜間施工が必要な工事 |
| 工期短縮補正 | 1.1~1.2 | 標準工期の80%以下での施工 |
これらの補正を適切に組み合わせることで、実態に即した共通仮設費を算出できます。たとえば、都心部の幹線道路で夜間施工が必要な工事の場合、基準率に対して1.5×1.3=1.95倍もの補正が必要となることもあります。
3. 積算基準の改定をチェックしない
積算基準は改定されているにもかかわらず、古い基準のまま計算を続けている企業が意外と多いのが実情です。国土交通省の「公共建築工事共通費積算基準」や各都道府県の積算基準は、社会情勢の変化に応じて定期的に見直されています。
最近の主な改定内容として、以下のような項目が追加・変更されています。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 働き方改革関連 | 週休2日制に対応した共通仮設費率の割増(4~7%加算) |
| 熱中症対策費 | 夏期施工時の休憩所エアコン設置、給水設備の充実 |
| 感染症対策費 | 消毒液設置、検温機器、パーテーション設置 |
| ICT活用 | ドローン測量、3次元データ作成費用の計上 |
2024年4月の改定では、建設キャリアアップシステム(CCUS)の導入費用も共通仮設費に含められるようになり、システム登録料や現場でのカードリーダー設置費用として、工事規模に応じて0.3~0.5%の加算が認められるようになりました。
共通仮設費の積算を効率化する方法
手作業での積算には限界があり、専門の積算ソフトウェアの導入は、もはや避けて通れない時代になっています。最新の積算ソフトは、単なる計算ツールではなく、AIを活用したインテリジェントな積算支援システムへと進化しています。
主要な積算ソフトの導入により、以下のような業務効率化が実現できます。
| 項目 | 詳細 |
|---|---|
| 自動料率設定機能 | 工事規模、地域、工期を入力すると、最適な共通仮設費率を自動提案 |
| 3D-CAD連携 | BIMデータから仮設計画を自動生成し、必要な仮設材の数量を算出 |
| 法令チェック機能 | 最新の労働安全衛生規則に基づく必要設備を自動でリストアップ |
| 見積書自動作成 | 積算結果から、提出用の見積書を瞬時に生成 |
ソフト選定時の重要なポイントは、自社の業務フローとの親和性です。カスタマイズの柔軟性、既存データの移行可能性、サポート体制の充実度などを総合的に評価し、段階的な導入計画を立てることが成功の鍵となります。特に、クラウド型のソフトウェアであれば、常に最新の積算基準に自動更新されるため、基準改定への対応漏れを防げます。
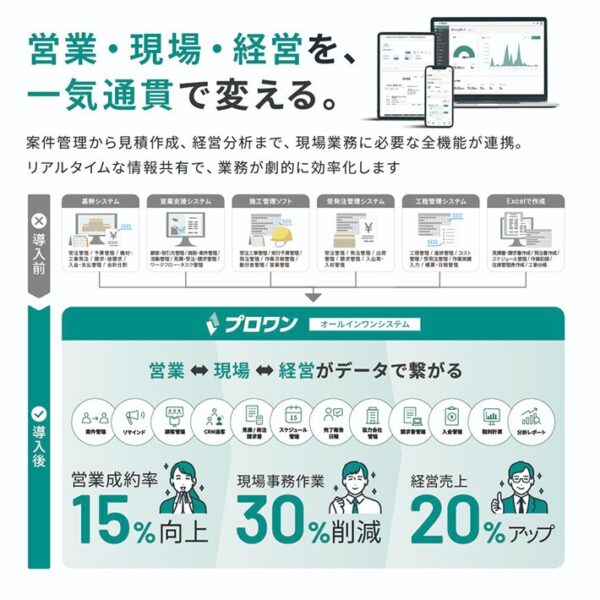
プロワンは、建設・設備工事・リフォーム・ビルメンテナンスなどの短・中期工事に特化した業務管理システムです。営業から施工・保守、請求・収支までの工程を1つのプラットフォームでつなぎ、現場起点のデータをリアルタイムに経営判断へ還元します。